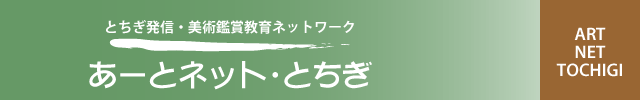第7回〈鑑賞ツール研究会〉の報告
日時◆2007年10月26日(金曜日)
◆18時30分〜
会場◆栃木県立美術館 普及分館ラウンジ
参加◆中学校教員 1名
◆美術館学芸員 4名
◆合計 5名
2007(平成19)年10月26日、第7回〈鑑賞ツール研究会〉が栃木県立美術館の普及分館ラウンジを会場に開催されました。
前回から引き続いて、美術館で発行している絵葉書に「投げかけキャプション」を組み合わせたキットの製作について実験を行ないましたが、今回はとくに、素材や技法、構成などについて問う「投げかけ」の言葉についてアイデアを出し合い、討議しました。
【今回の議題】
■絵葉書を用いた「投げかけキャプション」の実験(続き)
◆作品の素材や技法、画面の構成などに関する技術的な事柄を意識させる言葉を考え、付箋に記して作品の絵葉書に貼り、鑑賞者に投げかける言葉(「投げかけキャプション」の内容)として適当かどうかについて考察を進めたが、討議の過程で、現在の子どもたちの抱えるさまざまな問題点についても話しが展開した。
- 「どんな画材で描かれている?」
- 「最初にどこから描いた?」
- 「いちばん目立つのはどこ?」
- 「触ったらどんな感じ?」
●上記のような「投げかけの言葉」が、キャプションの内容としてリストアップされた。
●技術的な問題を意識させるとしても、子どもたちに、何がいちばんよいことかを考えるとき、改めて、鑑賞の目的はどうなるのか?
●鑑賞の方法(仕方)を教えることか。人格の形成に役立てることか。
●いまの子どもたちには空間を認識する能力(空間概念)が不足しているのではないか。
●数学の先生からも、そのような指摘を受けたことがある。
●現実のモノを見て、絵に描くという経験が不足しているのかもしれない。
●図工の時間に、写生やスケッチをすることがない学校もある。
●三次元の立体物を二次元の平面に表現する、あるいは逆に、二次元の平面に表現された対象を三次元の空間に立体化するなどの学習は、さまざまな意味で重要ではないか。
■「鑑賞ツール」の新しいアイデアについて
◆「投げかけキャプション」について討議している過程で、新たな課題が浮かび上がったことから、改めて、別種の「鑑賞ツール」のアイデアとして検討することとなった。
●小・中学生たちが、空間の概念を的確に認識し、とくに、立体を感覚として捉えるためには、どのような方法があるだろうか。実際に学校の先生から、どのようにしたらよいかという相談を受けたことがある。
●「造形遊び」などは、本来、そのような目的で行なわれているのではないか。
●しかし、現状での「造形遊び」の成果には、かなり問題があると言わざるを得ない。
●マンガやアニメの「フィギア」を作ることも、平面に表現された対象を三次元の空間に立体化するという意味では役に立つかもしれない。
●小・中学生たちに、立体的な空間概念を理解させるためのツールの開発が必要かもしれない。
●立体物を三次元空間の中で把握し、認識する能力は、対象を的確に捉えるために必要であり、絵画や彫刻の分野を問わず、鑑賞を深めることにつながっていく。
■次回の研究会
◆作品の絵葉書を用いた「投げかけキャプション」について、まとめを行ない、いよいよ実際の制作につなげるため、その具体的な詳細にまで検討を進める。また、新たな課題として浮上してきた、子どもたちにおける空間概念を理解する力の不足を補うためのツールについても、引き続き考えていきたい。